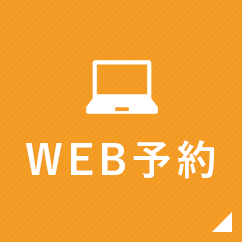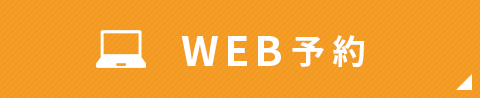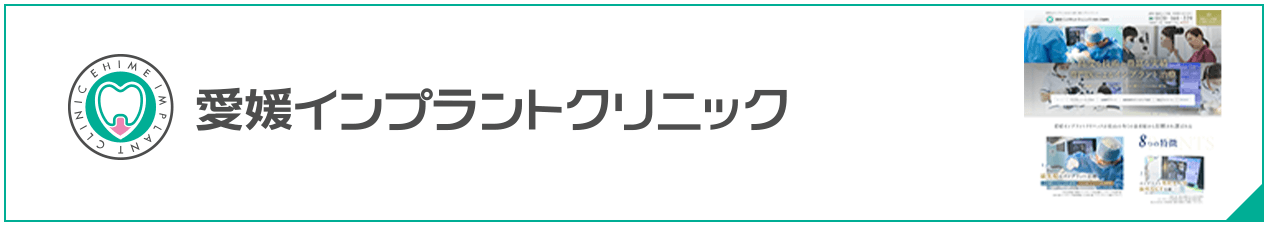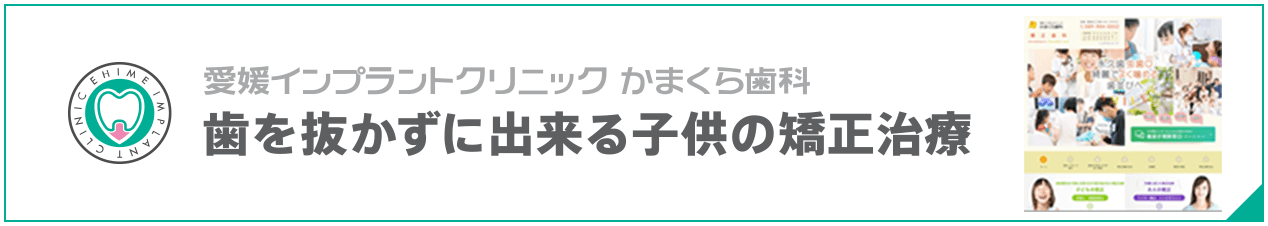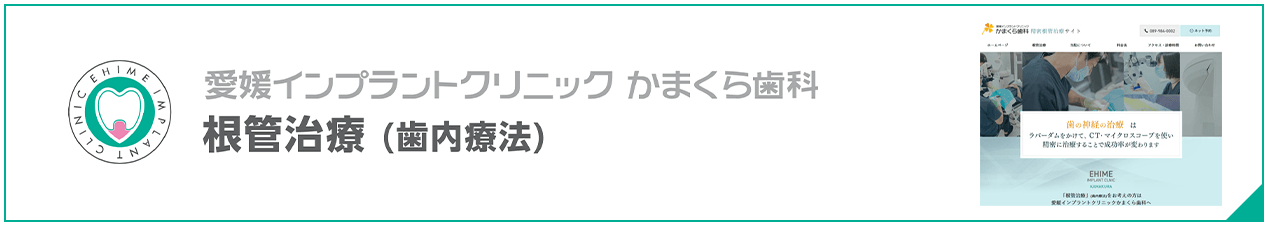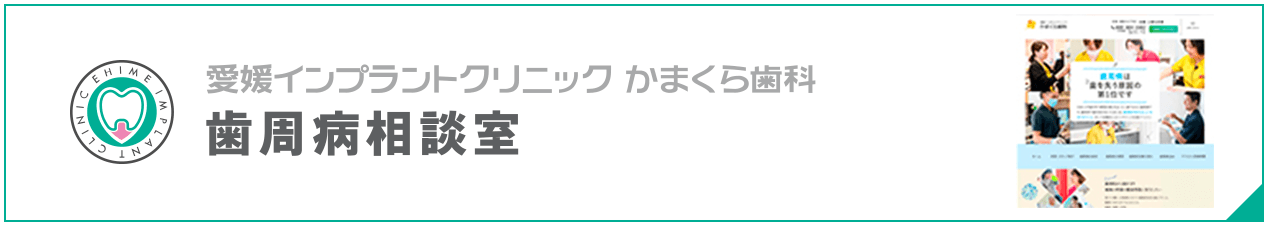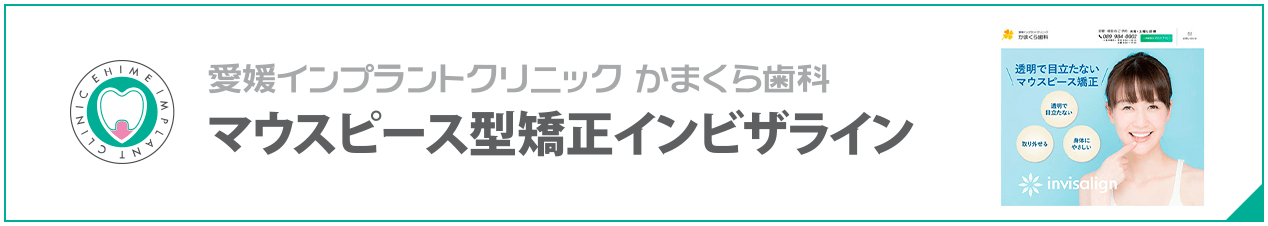なぜ歯は黄色くなるの?現代社会で求められるホワイトニング
2018年12月26日
みなさんは、自身の歯の色が気になったことはありませんか?若いころは白い歯だったのに、歳を重ねるにつれて、歯が黄色くなってきたと、ご相談くださる患者さまも多く見受けられます。では、なぜ歯はなぜ黄色くなるのでしょうか。現代社会で求められるホワイトニングと合わせてご紹介していきましょう。
現代社会で求められるもの
しっかりとアイロンがけされたYシャツ、洗練されたスタイリッシュなスーツ、清潔感のある髪型や笑顔などが一般的に社会人として求められていますが、近年では整った歯並びと同様に、白い歯が求められる傾向になりつつあり、欧米では既に審美的に美しくあるためだけではなく、虫歯や歯周病予防の一環として、不揃いな歯並びを矯正したり、黄色くなった歯を白くしたりすることが、最低限のマナーとして当たり前のようにおこなわれています。
歯が黄色くなるのはなぜ?
では、なぜ歯が黄色く変色してしまうのでしょうか。一緒に紐解いていきましょう。
【加齢】
歯はエナメル質、象牙質、歯髄で形成されていますが、歯の表面組織であるエナメル質は、白くはありません。みなさんが、歯が白いと考えるのも無理もありません。エナメル質は透明となっており、エナメル質の下の層にある象牙質はクリーム色をしています。象牙質は加齢とともにその厚みが増していき、色を濃くしていきます。半透明であるエナメル質から黄色くなった象牙質の色が透けてみえるために、歯が黄色くなったと感じるようになります。
【飲食物や嗜好品による着色】
以下の飲食物、嗜好品に影響により歯が黄色く変色する場合もあります。それら色素が歯の表面に沈着し、
・お茶
・ウーロン茶
・コーヒー
・ワイン
・タバコ
・カレー
【歯の神経の壊死・除去】
歯の神経が壊死または、除去したばあい、歯はだんだんと白さを失い黒くなっていきます。また、根管治療を終えた根管内に土台を入れた場合、その土台である金属の成分が溶け出し、歯が黄色くなるのではなく、真っ黒となってしまう場合もあります。
【薬の副作用】
マイコプラズマ肺炎などの疾患に効果があるといわれている抗生物質である「テトラサイクリン」は永久歯が生えかわる前に服用すると、テトラサイクリンの影響で生えてきた永久歯が左右対称に黄色く変色している場合があります。
ホワイトニングの種類
ホワイトニングの方法は、以下の通り3通りの方法になります。メリット・デメリットを理解し、自身に見合ったホワイトニングの方法を選択しましょう。
【オフィスホワイトニング】
歯科医院でおこなう、ホワイトニング方法です。歯科医師や歯科衛生士のみが取り扱うことのできる、高濃度な過酸化水素を含んだ薬品を歯に塗布し、歯の表面に沈着した色素を分解させ歯を白くさせる方法です。目標する白さを患者さまと確認後、数回にわけてホワイトニング治療をおこない理想の歯の色に近づけます。
【ホームホワイトニング】
ご自宅で患者さま自身がおこなうホワイトニング方法です。歯科医院などで歯型を採取し、オーダーメイドのマウスピースを作成します。マウスピース内にホームホワイトニング用の薬品を塗布し、定められた時間装着します。オフィスホワイトニングで使用する薬品より濃度は低く、歯を白くするには時間がかかりますが、毎日おこなうことで、およそ2週間で効果が表れてくるといわれています。
【デュアルホワイトニング】
オフィスホワイトニングをおこないながら、ホームホワイトニングもおこなうホワイトニング方法です。歯科医院への通院と、ご自宅での治療には手間がかかりますが、より早い期間で効果が現れ、なおかつその白さを長い時間維持することが期待できます。
【ホワイトニングをおこなえない人】
妊娠中、授乳中、無カタラーゼ症の人、エナメル質形成不全の人、象牙質形成不全の人、極度の歯周病の人、16歳以下の小児はホワイトニングをおこなうことはできません。
ホワイトニングのメリット、デメリット
メリットとデメリットを理解した上で、ホワイトニングをしましょう。
【メリット】
・審美的に美しくなる
・コンプレックスが解消される
・清潔感が増す
【デメリット】
・施術直後は「しみる」ことがありますが、一過性であり通常24時間ほどで症状は治まります。
・費用がかかる
・白さを永久に保つことは困難であり、色戻りする
ホームケア
上記でご紹介したホワイトニングをおこなっただけでは、白い歯を長い時間保つことは難しく、日々のホームケアが重要となります。またホワイトニング直後は通常時より着色しやすい状態となっているために、色素沈着が予想される飲食物、嗜好品は控えることをおすすめします。また、ホワイトニング後は、ホワイトニング専用の歯磨き粉を使用することで、色戻りを予防するこが期待できます。
【着色しにくい食品】
白米、パン、乳製品、白身魚、うどん、パスタ(ソースは別)
以上、ホワイトニングについてご紹介してまいりました。現代社会において、白い歯はエチケットとして考えられ、若い世代、働き盛りの世代を中心に、ホワイトニングを求める人が増加傾向にあります。これからおこないたいと考える人、興味がある人も、ご自身に見合ったホワイトニング方法を選択し、白い歯を手に入れましょう。
もう怖くない!お子さんも歯医者さんデビュー!
2018年12月19日
みなさん、子どもの頃に歯科医院に通われた経験はありますか?
白衣を着てマスクをした歯科医師、歯科衛生士などのスタッフが出迎え、歯科医院独特の薬品の香りと、「キーンキーン」と耳に残る歯科医院特有の機械音を考えると、お子さんが歯科医院を怖がったり、通院を拒否したりすることは、おおいに考えられることであり、歯科医院での診察を受けることを希望するも、お子さんが怖がって歯科医院に行くのを嫌がり困っている親御さんがいることも事実であります。そこで今回は、どうすれば小さなお子さんも怖がらずに歯科医院を訪れ診察をうけられるか、ご紹介していきます。
子どもはなぜ歯医者さんを怖がるの?
大人でも歯科医院を受診するのをためらってしまうものであり、小さなお子さんでは尚更、歯科医院を受診することに恐怖心や不安感を抱いてしまうのは、仕方がないことかもしれません。では、実際にどのような理由から、お子さんは恐怖心や不安感を抱いてしまうのでしょうか。
以下は、お子さんが歯科医院を怖がる代表的な理由となります。
診療チェアに座りたくない
歯科医院特有の診療チェアは、普段目にすることのないものであり、不安感を覚えてしまいます。
マスク・白衣姿が怖い
マスクは口元が隠れてしまうため、怖がるお子さんも多くいらっしゃいます。また、白衣は内科医や小児科医などでも目にする機会もあると思いますが、“白衣=注射(痛い)“イメージがあるのかもしれません。
何をされるのかわからない
診療チェアに座らされて、何をされるかわからない。「虫歯を治す」など治療の概念を理解できない年齢なら更にその傾向は強くなります。
注射をしたくない
虫歯治療などをおこなう際には欠かせないのが局所麻酔ではありますが、小さなお子さんから大人まで多くの患者さまが、恐怖心を抱いています。
薬の味がまずい
歯科治療では、薬品をお口の中に塗布することもあり、苦手意識を抱いてしまうお子さんも多くいらっしゃいます。
音が怖い
歯を削る音でもある「キーンキーン」という耳に残る音が苦手だというお子さんも多くいらっしゃいます。
上記のように、歯科医院の受診に恐怖心や嫌悪感を抱く多くの理由があげられますが、お子さんが歯科医院の受診を嫌がるからと言って、治療をおこたることは得策ではありません。なぜ、お子さんが歯科医院の受診を嫌がるのか、その理由を理解することが、重要となります。
歯医者さんの工夫
歯科医院では、小さなお子さんの歯科医院、治療への恐怖心を出来るだけ取り除くための工夫をしています。
声かけ
治療をおこなうときは、その工程、工程で「今から水がでるね」「音が鳴るよ」と、今からおこなう治療内容、工程内容をお子さんに分かりやすく伝えます。
お子さんの状況に寄り添う治療
泣いて嫌がるお子さんに、無理やり治療はいたしません。しかし、緊急時や治療を必ずおこなわなければならない状況の場合は除きます。
信頼関係
大人同様に、お子さんとの信頼関係も大切だと考えます。治療前にはコミュニケーションをはかり、治療へと繋げます。
歯医者さんは怖くない
「歯医者さんは怖いよ~」「虫歯になったら注射しなきゃいけないのだよ~」、こんな声かけを、歯磨きを嫌がるお子さんなどにされたことはありませんか?お子さんはみな繊細であり、大人の影響をすぐに受けてしまい、何気なく言った言葉であっても「歯医者さんは怖い、痛い場所」と、イメージづいてしまうものです。
歯科医院は「虫歯を治す病院」であり、虫歯を放置してはいけない、虫歯を治すために歯科医院に行くということをしっかりとお子さんに説明しましょう。年齢によっては理解できないことではありますが、そのような場合は、口を大きく開ける練習や、歯医者さんごっこなどをおこない、歯科医院を身近に感じられるようにしましょう。そうすることで、スムーズに検診や治療を受けられるようになれる近道となるかもしれません。
子どもの頃から歯医者さんに通う重要性
小さなお子さんは特に、歯科医院に行くことを嫌がる場合が多く見受けられますが、虫歯などの早期発見や、お子さんの歯磨きや口腔ケアの意識を高めるためには、歯科医院を受診することが何よりも重要であり、小さなころより歯科医院で診療を受けることで、定期的に歯科医院を訪れる習慣ができ、生涯に渡り自身の歯で美味しく食事をとることも可能となるのではないでしょうか。
以上、どうすれば小さなお子さんでも怖がらず、歯科医院を受診することができるのかをご紹介してまいりました。歯科医院は怖い、痛い場所というイメージを吹き払い、今から何のために、歯科医院に出向き、どんなことをおこなうのかを、お子さんにも根気よく説明しましょう。また、大泣きするからといって受診をおこたることはせず、虫歯など気になることがある場合には、ためらわずに受診しましょう。
妊婦さんに歯科検診をすすめる理由とは?
2018年12月12日
妊婦さんに歯科検診をおすすめする理由をご存知でしょうか。妊娠すると身体にさまざまな変化が現れるように、お口の中にも変化が表れやすくなり、注意が必要となります。「妊娠中に検診や治療をおこなっても大丈夫なの?」と、心配な声も少なからず聞こえてきます。そこで今回は、妊婦さんに歯科検診をおすすめする理由、妊娠中に歯科治療を受けられるのか、受ける際の注意点をそれぞれご紹介していきます。
妊婦さんに歯科検診をすすめる理由
最近の研究結果では、女性ホルモンの変化が歯周病に影響をもたらすと考えられています。女性の身体で大きな変化がある「思春期」「性成熟期」「妊娠期」「更年期」「老年期」には特に大きく女性ホルモンの活動が変化するために、お口の中のトラブルや疾患だけではなく、さまざまな身体のトラブルや疾患を引き起こす要因となっているとも考えられています。
特に女性ホルモンの分泌に大きな変化がある妊娠期には、歯科検診を受けることが推奨されています。なぜならば、妊娠期は悪阻(つわり)などの影響から食生活にも変化をもたらせるだけでなく、女性ホルモンである、エストロゲンやプロゲステロンなどが月経時に比べてそれぞれ100倍、10倍以上分泌されると言われています。
それら女性ホルモンは唾液や歯周ポケットと呼ばれる、歯と歯肉の間の溝から分泌される成分中にも含まれ、お口の中にさまざまなトラブルや疾患を引き起こす可能性が高くなることから、妊娠期の歯科検診がすすめられています。
妊娠時に現れやすい症状
では、妊娠期にはどのようなお口のトラブルや疾患の症状が現れやすいのでしょうか。症状別に解説していきましょう。
【歯肉が腫れたり、出血したりする】
女性ホルモンが多く分泌される妊娠期には、およそ9割の妊婦さんに、歯肉が腫れてしまったり、出血してしまったりする症状が現れていると言われています。このような妊娠期の歯周病は「妊娠関連性歯肉炎」と呼ばれています。
【冷たい、熱い飲食物でしみる】
歯周病のサインの1つです。虫歯でも冷たい、または熱い飲食物でもしみるような感覚が現れます。
【歯や歯肉が痛む】
虫歯がないのに、歯や歯肉が痛む場合があります。これもまた歯周病のサインの1つであり、普段歯肉に覆われていた刺激に弱い象牙質が、歯周病などにより歯肉が衰退し下がることで外部に露出し、すこしの刺激だけで痛みを感じてしまう場合があります。
【唾液がネバネバする】
妊娠期には唾液の分泌量は激減し、お口の中は酸性になりがちになり、唾液がネバネバするように感じます。唾液は飲食をするさいに消化を促すとともに、お口の中を洗い流す役目もありましたが、唾液の分泌量が減少したために、お口の中を清潔に保つことができなくなる可能性があります。
【悪阻(つわり)などの影響から、歯磨きができなくなる】
個人差はありますが、平均して妊娠初期から妊娠4ヶ月から妊娠5ヶ月頃まで悪阻(つわり)の症状が現れ、お口の中に歯ブラシを入れることに抵抗を感じる場合があり、歯磨きが適切におこなうことが困難になります。
【食事回数が増え歯垢(プラーク)が溜まりやすくなる】
悪阻(つわり)の症状が治まると、食欲が増す妊婦さんも多く、1回の食事量は減っても回数が増えた、間食をするようになるなど、食べ物を食べる機会も増え、歯垢(プラーク)が溜まりやすくなります。
妊娠中、歯科検診・治療を受ける時期や気を付けること
【妊娠中の歯科治療の時期】
妊娠初期から悪阻(つわり)の症状が落ち着くとされる妊娠4ヶ月から妊娠5ヶ月頃までは、不安定であり早急な治療が必要な場合を除き、歯科治療は避けるべきでしょう。
悪阻(つわり)の症状が落ち着く妊娠中期とされる、妊娠5ヶ月から妊娠7ヶ月の間に歯科検診や治療を受けることをおすすめします。妊娠後期になると、お腹がせりだし、診療ユニット(椅子)に座る、または仰向けになって治療することも困難になる場合も多く、早急に治療が必要な場合を除き、避けるべきでしょう。
また、体調も個人差があり、自身の身体とお腹の中の状況など考慮しながら、歯科医師と治療時期などを相談しましょう。
気をつけたい、避けたい検査・治療
【麻酔】
一般的に歯科医院で使われている歯科用麻酔薬は妊娠期にも投与が可能なものが多く、お口の中で使用する麻酔は局所で分解され。お腹の中の赤ちゃんには影響することはありません。麻酔で過去に気分が悪くなってしまう、効きにくい場合などは、歯科医師に相談しましょう。
【レントゲン】
レントゲン撮影に不安を覚える妊婦さんも多くいらっしゃいますが、口の中の
レントゲン撮影で浴びる放射線量はごく少量であり、口とお腹(子宮)との距離もあり、鉛の防護服(エプロン)でお腹を保護することで更に安心を得られます。
【薬の服用】
妊娠していることを歯科医師に伝え、妊娠期にでも服用できる薬を服用してもらいましょう。
【転倒】
お腹が大きくなるにつれて、転倒するリスクは高まります。歯科治療をするさいの、診療ユニットから転倒しないように、気をつけましょう。
以上、妊娠さんに歯科検診をすすめる理由、妊娠期に出やすい症状、検診や治療をうける時期などについて、ご紹介してきました。妊娠期はとてもデリケートであり自身の体調、お腹の中の赤ちゃんの状況なども産婦人科医、歯科医師と相談して無理なく歯科検診、治療をおこないましょう。
入れ歯を必要とする高齢者が減少?8020運動と予防歯科
2018年12月5日
日本人4人に1人は65歳以上という超高齢者社会に突入した現代の日本ではありますが、とある調査では、以前より入れ歯を必要としている高齢者は減少しているという、驚くべき調査結果が報告されています。なぜ、超高齢化社会である日本において、入れ歯を必要としている高齢者は減少したのでしょうか。そこで今回は入れ歯が必要な理由と、入れ歯を必要とする高齢者がなぜ減少するのか、ご紹介していきましょう。
入れ歯はなぜ必要なのか
歯は、人間として生きていく上でとても重要な組織であります。食べ物を噛み砕き胃の中に送り入れ栄養分とするために、なくてはならないものです。しかし、虫歯や歯周病が進行してしまうと、やがて歯を失ってしまいます。
歯(永久歯)を1本や2本失ったところで、なにも支障はないと考える人もいると思いますが、歯を1本失うだけで咬み合わせにずれが生じる場合や、1本抜けることでスペース(空間)が生まれてしまい、そのスペースに左右の歯が移動する傾向があります。
歯並びや咬み合わせがずれるだけで、食べ物が噛みづらくなってしまう場合や、周辺の歯や組織が抜けてしまった歯の役目を補うために過度に力が加わり、歯を支えている歯周組織(歯肉、セメント質、歯根膜、歯槽骨)を吸収し新たに歯が抜け落ちてしまう恐れもあり、歯(永久歯)が抜けたのにも関わらず、治療をおこなわず放置してしまうと、大変リスクをともないかねません。歯を抜けたまま放置している場合は早急に歯科医院で治療を受けましょう。
失った歯を補う補綴物はブリッジや部分入れ歯、総入れ歯です。ブリッジは抜けてしまった歯の両隣の健康な歯を2本削り、削った両隣の2本の歯を支えに人工の歯(ダミー)を設置し補う補綴物です。部分入れ歯は、装着するために健康な歯を少量削り、クラスプと呼ばれる金属のバネをかけて固定します。総入れ歯は上の歯はまた、下の歯すべての歯がない場合に装着する義歯のことです。
いずれも、歯周病や虫歯によって歯を失ったがために装着することになる補綴物です。
入れ歯を必要とする高齢者が減少した理由とは
では、なぜ入れ歯を必要とする高齢者が減少したのでしょうか。以前は「虫歯になったら歯科治療」というスタンスであり、厚生労働省「歯科疾患実態調査」の調査結果から推測されるように、1993年当時の65歳以上74歳までの人たちの残存している歯の数は平均して11.8本であり、永久歯全28本中(親知らず入れると34本)16本もの歯を失っている結果となり、入れ歯を使用しなければ、満足な食生活が送れない状況であったことが想像できます。
しかし1999年当時の65歳以上74歳までの人たちの歯の残存数は15本、2005年には16.8本、2011年には19.3本、2016年には20.8本となり、永久歯全28本(親知らず入れると34本)中、65歳から74歳まで平均して20.8本もの歯を維持できるようになったと調査結果から推測できます。
なぜこれほどまでに残存数を増やすことができたのでしょうか。その理由はやはり現在の歯科医療にも反映されている、「8020運動」と「予防歯科」の普及ではないでしょうか。「8020運動」とは、1989年厚生省(のちの厚生労働省)が永久歯20 本あまりあれば、食べ物を自身の歯で噛み砕き、美味しく食事ができると考えられることから、“80歳で20本の歯を維持しよう“と活動をはじめたものであります。
人間にとって“食”は生きるために必要なものであり、自身の歯で食べ物を噛み砕き、美味しく食べ栄養を摂取することが健康にも繋がります。部分入れ歯や総入れ歯である義歯を装着して食べ物を噛み砕く力は、自身の歯で噛み砕く力より40%も低下してしまい、十分に噛み砕くことができなくなる可能性が高くなります。
「8020運動」を遂行するには、「予防歯科」がとても重要となります。虫歯になってから、歯周病が進行してから治療だけをおこなっているだけでは、80歳で20本もの歯を維持することは困難であり、日頃からの「予防歯科」が80歳までの残存数を左右させます。
予防歯科では定期的に歯の表面のクリーニングをし、虫歯や歯周病の原因であるプラークの除去や定着を防いだり、歯ブラシでは除去することができない歯石をスケーリングで除去することで、新たな歯垢の定着を防いだり、正しい歯磨き方法を指導することで患者さまの口腔清掃への意識を高めるなどの「予防歯科」を各歯科医院が積極的におこなうようになりました。
調査を始めた1993年当時の75歳から84歳の歯の残存数は6.2本でありましたが、1999年には8.6本、2005年には10.1本、2011年には14.2本、2016年には16.9本となり、およそ30年あまりのうちに約10本もの歯を多く維持できるようになり、80歳で自身の歯を維持できている割合は初めて50%をも超える結果となり、入れ歯を必要とする高齢者は減少していることに繋がります。
今後の課題
今後も更に健康な歯を維持し、生涯にわたり1人でも多くの人々が美味しく楽しく食事ができるように、「8020運動」や「予防歯科」は推奨されていきます。虫歯や歯周病に罹患するリスクを低減させ、入れ歯を必要とすることのないように、日々の口腔ケアをおこなうことが大切です。